事業継承とは、企業や事業の経営権を現経営者から後継者に引き継ぐことです。経営者の高齢化が進み、中小企業の後継者問題は深刻といわれていますが、会社を存続していくためには、かかせないものなので悩んでいる人もいるのではないでしょうか。
今回は、事業承継の最適な順番やどのような人が後継者にふさわしいのかなど詳しく説明していきます。ぜひ、最後まで読んで参考にしてください。
事業承継について
事業承継とは
冒頭でも説明しましたが、事業承継とは企業や事業の経営を現経営者から後継者に引き継ぐことです。
事業承継で引き継ぐものには、会社の経営権や資産だけではなく、経営理念・会社の文化などがあります。
また、後継者には子どもなどの親族に限らず、従業員または第三者(外部の経営者)も含まれます。
事業承継するメリットや効果
- 後継者が経営を引き継ぐことで事業を継続できる。
- 雇用維持が前提のため、従業員や取引先への影響を最小限に抑えられる。
- 新しい視点やスキルを持つ後継者による経営改善が期待できる。
事業承継する際の最適な順番
事業承継する際の具体的なステップとしては、次のような順番が最適です。順番にみていきましょう。
- 事業の財務状況や経営資源を整理・確認するなどの現状分析をする。
- 親族、従業員、外部候補の中から後継者の候補を選定する
- 将来の目標や課題を整理し、引継ぎ後の事業計画を明確化する。
- 事業承継までの具体的なスケジュールを策定する。
後継者を選ぶ際の条件や注意点

後継者の選定基準や条件は、どのようなものがあるのでしょうか。全部で5つありますので詳しくみていきましょう。
1.リーダーシップ、問題解決力、意思決定力などの経営能力
会社のトップに立つのであれば、優れた人間性が求められます。会社を引っ張っていくリーダーシップはもちろん、トラブルが起きた際の問題解決力や物事を決める意思決定力がとても重要です。
2.自社の製品やサービス、業界特性の理解度が高い
自社の工場ではどのような製品が作られているのか、自社のサービスにはどのようなものがあるのかを把握しておく必要があります。また、これは1つの部署だけではなくさまざまな部署の理解を深めておくことも大事なポイントです。
3.従業員や取引先との信頼関係を築けるかなど人間関係の構築力
従業員や取引先との信頼関係がなければ会社のトップには立てません。会社のトップに立つ人は、従業員や取引先のことも考えなければならないのです。責任感を持って人間関係を構築できる人が向いています。
4.事業を継続させる意志と意欲
事業を継続させるには、会社を倒産させないように、さらに成長していけるようにと強い意志と意欲がなければなりません。
5.経営理念の理解
会社のトップにつくのであれば、会社の経営理念を理解し共感しなければなりません。経営者が変わったからといって、会社に深く根付いた経営理念がすぐに変わることはありませんので、経営理念に理解がなければ難しいでしょう。
後継者を選ぶ注意点としては、候補者がプレッシャーを感じすぎないように配慮し、多角的に適性を判断するために複数人で評価を行うのがよいでしょう。
また、後継者を選ぶことはとても重要なことです。慌てずにすむように、事前に考えてはやめの準備をすることが必要です。
後継者の育成方法
後継者の育成方法には次のようなものがあります。
- 各部署での実務経験を通じて事業全体を把握してもらい、現場経験を積ませる。
- 研修プログラムを実施し、経営に必要なスキル(財務、マーケティング、法務など)を学ばせる。
- メンター制度を導入し、現経営者や外部の専門家が指導役となり、実務を支援する。
- MBAやセミナー(外部教育)に参加させ、経営理論を学ばせる。
事業承継でよくあるトラブル
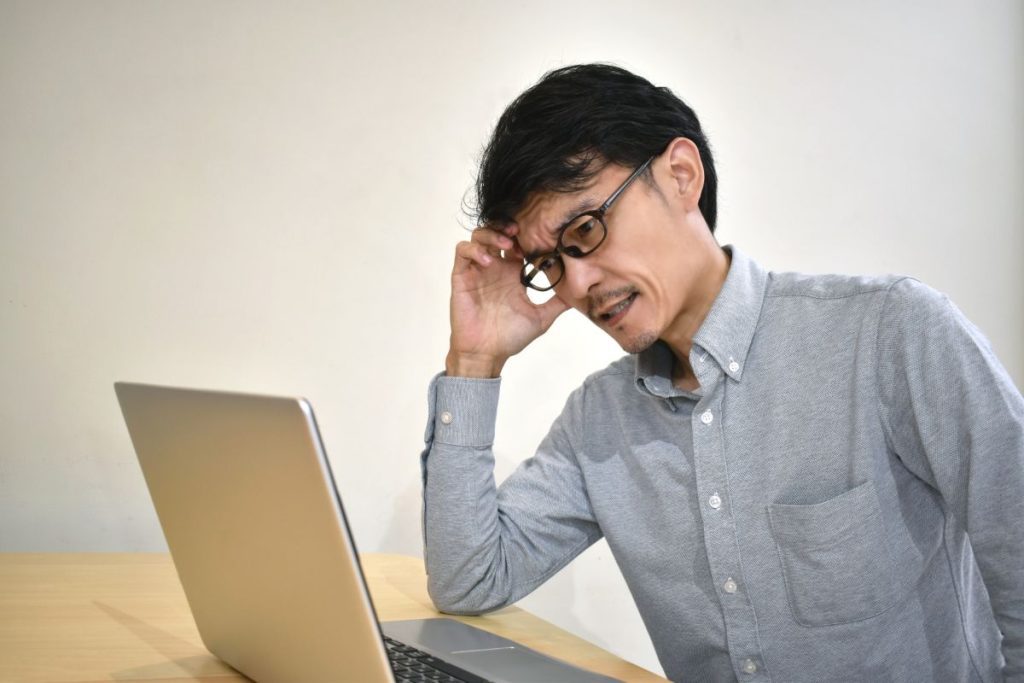
事業承継でよくあるトラブルを紹介していきます。
後継者候補がいないなどの後継者不足
中小企業の高齢化が進んでいるため、後継者候補がおらず後継者が不足している事態になってしまっている企業が多いです。
解決策としては、後継者不足を解消するために外部のM&Aや後継者人材バンクを活用することが必要です。
後継者が受け入れられないなどの従業員の不満や反発
会社のトップが変わり後継者が従業員に受け入れられず、不満や反発が起こります。その場合、最悪会社を辞めてしまうケースもあります。
解決策としては、従業員と透明な情報共有と信頼関係の構築を行うことです。
相続税や贈与税が高額になるなど税金面での負担
会社を後継することで、相続税や贈与税が高額になることがあります。
解決策としては、事業承継税制を活用し、税負担を軽減することです。
事業承継は専門家に相談するのがオススメ

専門家に相談された場合、経営戦略や税金対策を含めた事業承継計画をサポートしてくれ、財務状況の整理・分析を元に、円滑な引継ぎを支援してくれるでしょう。
また、契約書や税制優遇措置の適用方法など法務・税務におけるアドバイスも提案してもらえます。
相談のタイミングですが、遅くとも事業承継の5年前には始めるのが理想的ですが、後継者選定に悩んだときや財務問題があるときは早期に相談するのがよいでしょう。
事業承継に関連する税制優遇措置や支援制度
事業承継に関して税制優遇措置や支援制度には次にあげるものがあります。代表的な例を紹介していきます。
事業承継税制
自社株の相続や贈与にかかる税負担を軽減する。
例えば「特例承継計画」を提出することで、納税猶予が受けられます。
M&A支援制度
中小企業庁が実施する「事業引継ぎ支援センター」を活用しましょう。
融資支援
承継後の事業資金に対する低金利の融資制度です。
初心者が事業承継で失敗しないようにするには
最初に取り組むべきこととしては、自社が何を目指しているのか、先ずは経営目標を確認し、それを明確化することです。そのあとに、後継者選定を行い、候補者の可能性を広く検討した上で、事業承継に特化した支援機関やコンサルタントなどの専門家に早期に相談することをオススメします。後継者の候補が決まったら、早い段階で後継者育成をすることも重要なポイントです。
失敗しないための心がけとしては、時間的余裕を持って準備し、状況に応じて柔軟に事業計画を見直した上で、後継者や従業員、取引先とのコミュニケーションを頻繁に取るのがよいでしょう。
後継者選びは事前の準備が重要
会社が経営を維持していくためには、事業承継はかかせません。会社にとって後継者選びは、会社を存続できるかどうかがかかったとても重要なことなのです。しかし、経営者は後継者を考えるのはまだ早いと後回しにしがちです。
いざ事業承継するときになってから、準備をしてなくて慌てることがないよう、事前に準備しておくことを念頭にいれておいてください。
また、先ほども説明しましたが不安や疑問点がある際には専門家に相談することをオススメします。
後継者選びをさまざまな視点からサポートできるのは、専門家しかいません。
早めの相談をして、しっかりとしたサポートをしてもらうことが後継者選びを成功させるコツです。

