福祉車両の購入を考えている方の中で、利用者に合った選び方やカスタマイズ方法がわからないと悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
福祉車両は介護を必要とする方、高齢者、子育て中の家庭など、利用者のニーズに応じて、選び方やカスタマイズの方法が異なります。この記事では、福祉車両の基本的な選び方や利用者別のカスタマイズ事例をわかりやすく解説します。購入前に知っておきたい注意点にも触れますので、福祉車両の購入を検討している方は、ぜひ最後までお読みください。
福祉車両の種類と選び方

利用者に合った福祉車両を選ぶためには、利用者にどのような装備が必要なのかを明確にすることが重要です。以下で福祉車両の主な種類と選び方について解説します。
福祉車両の主なタイプ(車いす対応/セカンドシート型など)
福祉車両には、大きく分けて以下のようなタイプがあります。
- 車いす対応タイプ
車いすのまま乗車できるタイプです。スロープやリフトを使って車いすを乗せ、そのまま車内で固定して移動します。車いすユーザーが自分で移動できない場合や、座席移動が困難な場合に適しています。 - セカンドシートリフトアップ型
車両の2列目の座席(セカンドシート)が回転して昇降することで、乗り降りをサポートするタイプです。歩行はできるものの、足腰に不安のある方や高齢者に多く利用されています。
- 助手席リフトアップ型
助手席が回転しながら昇降して、乗り降りをサポートするタイプです。足腰に負担を感じる方や、車いすとの移乗が必要な場合に適しています。
- 回転シート型
シートが回転することで、乗り降りの動作をサポートするシンプルなタイプです。シートの昇降機能がなく、足腰がある程度動かせる方に向いています。
利用者の身体条件や使い方に合った選び方
福祉車両を選ぶ際は、利用者の身体条件や使用シーンを具体的に考えることが大切です。ここでは、利用者に合った選び方のポイントを紹介します。
車いすでの乗り降りのしやすさや車いすのサイズを確認する
使用している車いすの大きさやリクライニング機能の有無によっては、対応できない車種もあります。実際に利用者本人、または同じくらいの体型の方が車いすに乗った状態で試乗し、天井の高さやスロープの角度を確認すると安心です。
介助者の使いやすさや負担を考慮する
介助者の使いやすさや負担の軽減を考慮することも大切です。電動ウィンチが付いている車両であれば、自動で車いすを車内へ引き上げられるため、介助者の負担を大きく軽減できます。介助者が実際に操作してみて、使いやすさを確かめることをおすすめします。
車両のフロア形状や天井高
一般車両を後から改造する場合は、フロア形状や天井の高さに注意が必要です。一般車両はフロアが高く天井が低い傾向があるため、車いすに乗ったままの利用者が頭をぶつけてしまう危険があります。こうしたリスクを避けるためにも、できるだけメーカー標準の福祉車両を選ぶと安心です。
利用者に合ったカスタマイズの例

利用者に合わせたカスタマイズを行うことで、福祉車両はさらに使いやすく、安全で快適な移動が可能になります。ここでは、利用者のニーズに応じたカスタマイズ事例を紹介します。
車いすユーザー向け:スロープ・リフトや固定装置
車いすユーザー向けのカスタマイズでは、乗り降りのしやすさと安全性が重要です。
スロープタイプは車両の大きさに左右されにくく扱いやすいのが特徴です。車体の高さによっては、角度が急になる場合があります。
リフトタイプは床面とほぼ平行に上下するため、安定感があります。リフトを搭載するためには大型車が必要になるケースが多く、駐車スペースにも配慮が必要です。
車いす固定装置にはワイヤー式やベルト式、ワンタッチ式があり、手動式と電動式があります。購入前に実際に操作して、使いやすさを確認することをおすすめします。新車ではオプション扱いとなる場合もあるため、事前の確認が大切です。車いす固定装置は、正しく使うことで安全性が確保できます。取扱説明書や操作動画で正しい使い方をしっかり確認しましょう。
高齢者向け:低床化・自動ドア・手すり
高齢者向けのカスタマイズでは、乗り降りの際に腰や膝への負担を軽減する工夫が欠かせません。ステップや手すりを追加すると、乗り降りの動作が安定しやすくなります。これらの装備はメーカー標準で付いている場合もありますが、必要に応じてオプションや後付け改造を検討するとよいでしょう。
さらに、自動ドアを採用すれば、ドアの開閉にかかる力が減り、介助者の負担も軽くなります。こうした装備を整えることで、乗り降りがスムーズになり、安全性も向上します。標準装備やオプションの内容はメーカーや車種によって異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
子育て・介護者向け:回転シート・チャイルドシート・荷室拡張
子育てや介護を担う家庭には、回転シートやチャイルドシートの追加、荷室の拡張が便利です。
回転シートは、介助者が子どもや要介護者を楽に乗せられる便利な機能です。ただし、昇降機能がない場合は福祉用途としての要件を満たさず、課税対象となるため注意が必要です。一方で、昇降機能付きで車いす固定ベルトも備わっている場合は、車両代が非課税となります。購入時は、昇降機能と車いす固定ベルトの有無を必ず確認しましょう。
回転シートの耐荷重は多くが100kg前後で、それを超える場合はリフトや他の仕様のシートを検討する必要があります。耐荷重が100kgを超える回転シートは後付けが可能で、多くは海外製品が使用されます。その際の車検は、ヨーロッパ基準で受ける必要があります。
チャイルドシートを追加する場合は、取り付ける位置や安定性に注意が必要です。エアバッグのある助手席はなるべく避けるなどして、取り付ける座席を慎重に選びましょう。
また、荷室を広げるカスタマイズを行えば、ベビーカーや介護用品などの大きな荷物を積みやすくなり、日常の利便性が向上します。
購入時のチェックポイント
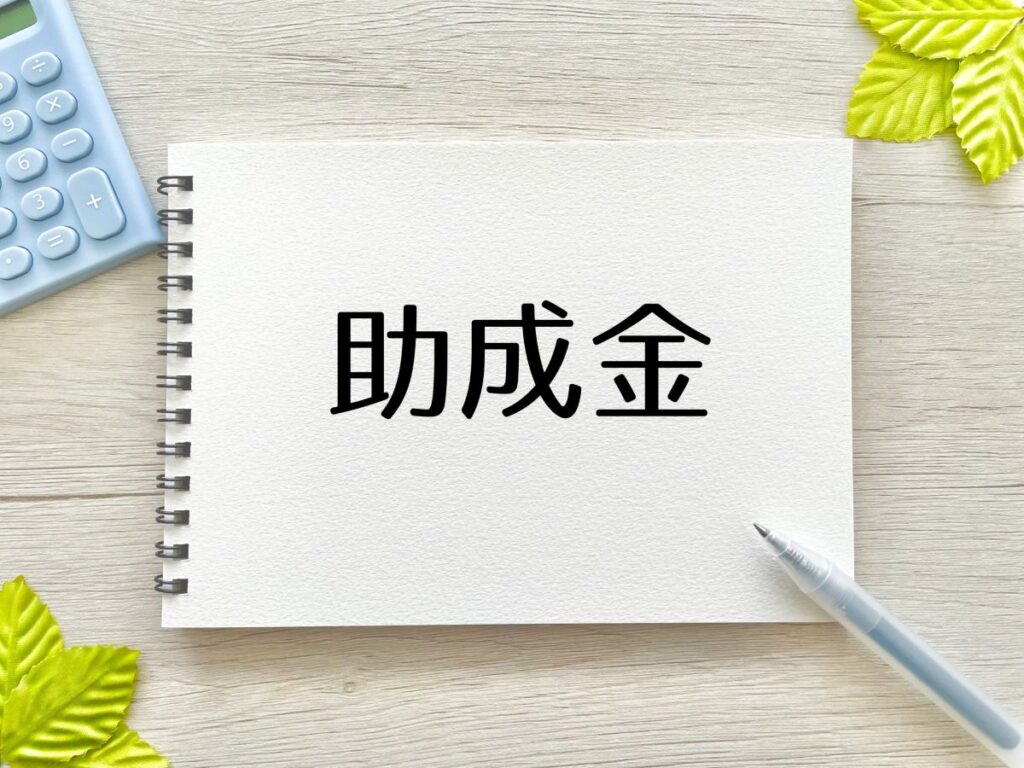
ここでは、購入前に押さえておきたいチェックポイントを整理し、費用面や手続きで失敗しないためのポイントを解説します。
見積もりで注意すべき項目(改造費用・オプション費用)
見積もりを取る際は、基本費用に含まれる項目とオプション費用が発生する項目を明確にしましょう。スロープやリフト、固定装置、ステップや手すりなど、必要な装備がオプション設定になっている場合があります。アフターサービスや保証内容もメーカーや販売店によって異なるため、事前にしっかりと確認しておくと安心です。後付け改造で海外製の部品を使用する場合は、アフターサービスが受けにくいことがあるため、注意が必要です。
公的補助金や助成制度の活用方法
福祉車両の購入や改造には、公的補助金や自治体の助成制度が利用できる場合があります。制度の内容や対象者、助成額は自治体によって異なります。購入前に申請が必要な場合も多いため、事前に自治体に確認しておくと安心です。
申請には見積書や障害者手帳の写し、車検証などの書類が必要になることがあります。また、申請期限が設けられている自治体もあるため、早めに手続きを行いましょう。販売店や自治体の窓口に相談しながら進めると、初心者でもスムーズに申請できます。
導入後のメンテナンスと安全対策
福祉車両を安心して長く使い続けるためには、日々のメンテナンスと安全対策が大切です。購入後に意識しておきたいポイントを紹介します。
定期点検で長持ちさせるコツ
福祉車両を長く安全に使うためには、定期的なメンテナンスが欠かせません。日常的には、スロープやリフトなどの福祉架装部分をこまめに清掃し、汚れや異物がたまらないようにしましょう。汚れは故障の原因になることがあるため、掃除機や拭き掃除でしっかり手入れをします。その際、装置を実際に動かして、異音や動作不良がないか確認することも大切です。専門業者での点検は年1回程度を目安に行い、内部清掃や消耗部品の交換をすることで、長く安心して使い続けられます。
緊急時の備えと保険の確認
緊急時に備えて、車載工具やジャッキ、三角表示板などの装備がそろっているかを確認しておきましょう。さらに、福祉車両専用の自動車保険やロードサービスに加入しておくと、万が一のトラブルのときも安心です。
利用者に合ったカスタマイズで安全・快適な移動を
福祉車両は、利用者の身体状況や使う環境にしっかりと合ったタイプを選ぶことが大切です。必要に応じてカスタマイズを加えることで、毎日の移動がより快適で安全になります。車両を選ぶ際は、実際の使用場面を具体的にイメージしながら、使いやすさを丁寧に確認しましょう。そうすることで、利用者も介助者も、安心して長く使える理想の一台を選べます。

